代表挨拶
株式会社機能評価Lab、代表取締役の工藤雅己です。
弊社のホームページを訪れていただき、ありがとうございます。
私たちは病院機能評価の新規受審、更新受審のご支援を中心として、全国の病院様にコンサルティングをご提供しています。
病院機能評価に合格する、より高い評価を受ける、ということを第一に大切なこととしておりますが、あくまで病院様にとってそれは手段であるとも考えています。
目的は患者さんに良質な医療を提供すること、そこをぶらしてはいけません。
病院機能評価のために職員の負担が増え、継続できない無理な制度や仕組みを作ってしまっては本末転倒です。
弊社では、職員の負担を減らし、継続できる仕組みを整えられるよう、7つのコンサルティングポリシーを掲げてご支援をしています。
ここでは、代表挨拶に代えて7つのコンサルティングポリシーをご紹介します。
1.無理・むら・無駄をなくします。
病院機能評価も年々求められるレベルが高まってきています。「病院機能評価のために」という言葉のもと、無理な仕組みを作り、継続できない病院様も見てきました。
機能評価が終わっても継続できる、コンサルティングが終わっても継続できる、という無理のない制度に落とし込めるかどうかがポイントです。私たちは無理な仕組みとならないようなご支援を心がけています。
また、5年も経つと各病棟の職員が入れ替わり、病棟独自ルールが常態化していることも珍しくありません。病棟に限らず、部署ごと、医師ごとにも然りです。独自ルールが蔓延するほど業務にむらが生じ、インシデント・アクシデントにも影響を与えます。病院機能評価をきっかけとしてこのような“むら”を排除し、院内統一ルールを再度明確化させていきましょう。
「以前からずっとこの方法で続けているので」という言葉もご支援先でよく耳にします。無駄とわかっていながらなかなか改善にまで手が回らない、中には、従前の方法に慣れすぎていて、無駄であることにすら気づかなくなっていることも珍しくありません。私たちがご支援することで、多くの病院様でのスタンダードを共有し、他病院の好事例を踏まえた改善提案をすることで、長年の無駄をなくしていきます。
2.手段が目的化しないように支援します。
「薬剤保冷庫の温度記録はつけていますか?」、「薬剤の期限切れは定期的に確認していますか?」このような質問からでも、手段の目的化が浮き彫りになったりします。
薬剤保冷庫の温度記録はつけていても、実際の適温範囲を知らず、適温から逸脱しても気づかなければ何の意味もありません。
救急カート内の薬剤の期限が切れていないか確認するために、アンプルに記載された有効期限が真上になるように並べ、薬剤名が一切見えない救急カートになっている病院様もあったりします。これでは緊急時に速やかに、薬剤を間違えずに使用する、という目的が果たせません。これらは氷山の一角ですが、病院内でも手段が目的化してしまっていることは山ほどあります。
私たちのご支援では、「その確認の本来の意味は?」、「その記録を残す目的は?」というところをしっかりとお伝えすることで、手段が目的化しないようにご支援しています。
3.第三者という立場を大切にします。
院内で病院機能評価の準備や業務改善などを行う際に、もっとも難しいことは、「私からは言いづらい」ということだったりしませんでしょうか。院内の立場、職種の違いなどもさることながら、病院機能評価でどこまで求められているのかわからないため、自信を持って提言できない、というお声もよく耳にします。私たちは第三者の立場として、必要なことを必要な場で、最適な方へご提言します。それが第三者の我々に求められていることだと考えています。
また、改善を進める上で、特定の分野の専門家を紹介してほしいというご相談をいただくこともあります。そのような際も第三者という立場を大切にし、利害関係なく最適な専門家におつなぎすることができます。これらは、親会社や関連会社がない弊社独自の強みだと考えています。
4.言いっぱなしにはしません。
コンサルティングというサービスを聞いて、どのようなイメージを抱きますでしょうか。私たちが一番思われたくないイメージは、「机上の空論」、「口先だけ」というようなコンサルティングです。つまり、口では理想論を語るが現実的ではない提案、言うだけ言って、その後に責任を持たない提案はしたくありません。言いっぱなしにせず、実現に向けて皆様と一緒に考えていきます。
また、私たちはコンサルティングの後に、必ず詳細な報告書をご提出しています。もちろん、報告書を出して終わりではありません。長期間のコンサルティングであれば、以前にお伝えしたことがその後どうなったかまで時系列で追うことができるような報告書の構成としています。言いっぱなしにせず、お伝えしたことがしっかりと仕組化できるまでご支援することをモットーとしています。
5.その場しのぎの改善策はご提案しません。
冒頭でも述べたように、私たちは病院様が病院機能評価に合格する、より高い評価を受ける、ということを第一に大切なこととしておりますが、「受かるためだけの支援」はしておりません。小手先だけのテクニック、審査当日だけしのげれば良いようなアドバイスを求める病院様は、弊社のコンサルティングは合わないかもしれません。
その場しのぎの改善策ではなく、長期的に継続可能な方法で、受審後も、ご支援終了後も職員の皆様で実践できる改善策をご提案することを心がけています。
受審時期が近づけば近づくほど、まずは受かること、を目標にしてしまいがちですが、ここでも手段が目的化しないよう、着実に質の高い医療を目指していくことが本来の病院機能評価受審の意義だと考えてご支援に臨んでいます。
6.担当者の方を独りにはしません。
病院機能評価は、病院全体で職員一丸となって取り組むものです。しかし、各項目の担当者レベルでは、皆さん孤独と不安の中で取り組んでいらっしゃいます。プロジェクトリーダーを任される副院長先生クラスをはじめ、各部署のトップの方々、病棟概要確認やケアプロセスを任される師長さんや主任さん、医療安全や感染管理を任される看護師さん、窓口や全体調整を任される事務の方々まで、それぞれの役割の中ではみな責任を背負っていらっしゃいます。そんな方々を、私たちは独りにしません。不安に寄り添い、一緒になって取り組んでいきます。
病院にも、相談窓口があります。患者さんが日々抱えている不安を聞き、寄り添って治療に向かうのが相談員であり、看護師であり、医師、スタッフの皆さんです。同じように、病院機能評価に取り組むすべての方々に寄り添い、一緒に改善するのが私たちの仕事です。
7.最後まで諦めません。
私たちは、短期的には、認定証が届くまで、決して諦めません。長期的には、病院様に医療の質を高めたいという思いがある限り、決して諦めません。
病院機能評価の準備・対策は、受審の前日まで、と思い込んではいませんか?当日にだって、改善ができます。サーベイヤーから指摘をされても、それはあくまで今日までの結果です。今日からまた変えれば良いのです。すぐに話し合って、対応と新しい方向性を検討することだってできます。指摘されたら終わり、ではなく、最後まで諦めずに取り組む姿勢が大切です。
私たちも、たとえ受審の結果にC評価があったとしても、改善して認定がされるまで、追加の支援料などは一切いただかずに責任を持ってご支援いたします。
ぜひ一緒に、病院を良くしていきましょう。
会社概要
| 会社名 | 株式会社機能評価Lab |
| 所在地 | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1アルコタワー7階 |
| 代表取締役 | 工藤雅己 |
| 事業内容 |
|
| 営業時間 | 8:30~18:00 ※模擬審査中などはタイムリーなご返答ができない可能性がございます。 |
ロゴに込めた思い
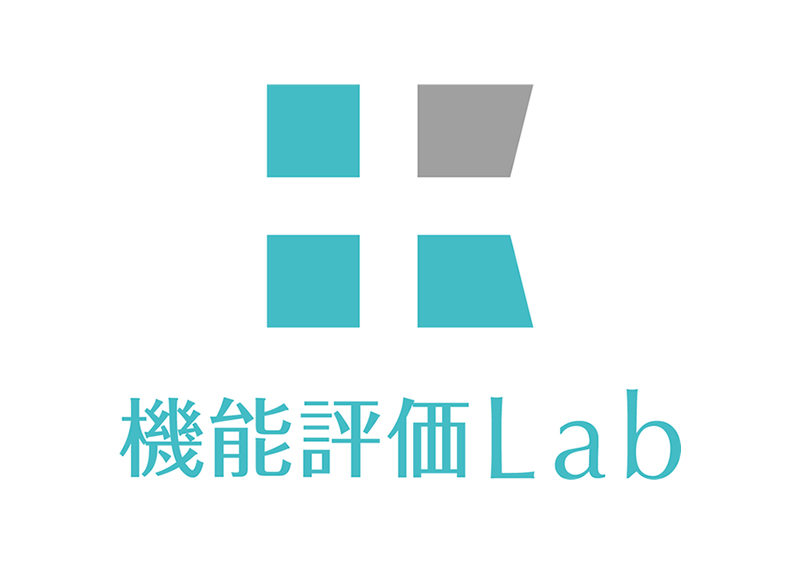
知的、公平性、信頼感をイメージした青色を基調に、機能評価や創業メンバーのシンボルアルファベット「K」をあらわすロゴにしました。
また、Kの中には、私たちのご支援先である病院様を連想する十字のマークをさり気なくあしらい、病院様と一体となって医療の質向上に貢献する、という思いを込めました。
また、ロゴの右上の色を変化させることで、「右肩上がり」というメッセージを込めました。継続した質改善により、前回受審時よりも更に高い評価を受けられること、そして昨日よりも今日、日々、右肩上がりで医療の質を向上できることを目指してご支援に臨む、という私たちの宣言も織り込まれています。
機能評価Labは、キノウヒョウカラボ、と読みます。
病院機能評価だけでなく、病院のあらゆる機能を研究する研究室をイメージした社名です。
医療が日々進化するように、私たちも、日々、勉強、研究を重ね、コンサルティング技術を磨いてまいります。
